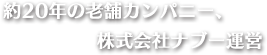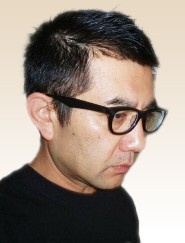感謝のお便り:青龍子先生
2022-08-31
お客様からのお便り
富嶽三十六景を始め
余白や空白を大事にしていた
書院造の違い棚の空間も、日本人の粋の原形を感じますね
詰め込みすぎない美、というものは
ミロのビーナスの腕がないのが偶然そうなったにしろ、無いことによる自由、無を見る人の脳に委ねる、作者だけで決定しない
粋なはからいというのは
その人の心を汲み取るだけで感動や感激を呼び起こしますね。
神奈川沖浪裏は、黄金比で構成され、その美を自然に体現した北斎は天命に則り生きたのだと思います。
理解を求めるのではなく、感性に委ねることを
自分も現していきたいです。
剣術の流派も皆伝された人が居なければ途絶えてしまいますね。
師範、師匠、家元、親方、大将、
人に繋ぐ見えない精神、技術。
芸術も製法を問うことは野暮で、秘匿性の神秘領域がありますね。
現代の資本主義とは真逆なものを感じます。
生きていた証。
先生のお話で、抽象的思考をより深い領域で捉えることができました。
ありがとうございました。
余白や空白を大事にしていた
書院造の違い棚の空間も、日本人の粋の原形を感じますね
詰め込みすぎない美、というものは
ミロのビーナスの腕がないのが偶然そうなったにしろ、無いことによる自由、無を見る人の脳に委ねる、作者だけで決定しない
粋なはからいというのは
その人の心を汲み取るだけで感動や感激を呼び起こしますね。
神奈川沖浪裏は、黄金比で構成され、その美を自然に体現した北斎は天命に則り生きたのだと思います。
理解を求めるのではなく、感性に委ねることを
自分も現していきたいです。
剣術の流派も皆伝された人が居なければ途絶えてしまいますね。
師範、師匠、家元、親方、大将、
人に繋ぐ見えない精神、技術。
芸術も製法を問うことは野暮で、秘匿性の神秘領域がありますね。
現代の資本主義とは真逆なものを感じます。
生きていた証。
先生のお話で、抽象的思考をより深い領域で捉えることができました。
ありがとうございました。
先生からの返信
※先生のからのコメントあり
(こちらのコメントは、投稿者のみご覧になれます)
(こちらのコメントは、投稿者のみご覧になれます)
※本サイトに掲載している写真・画像、全ての内容の無断転載・引用を禁止します。
メール占い専門館 (c)NABOO Inc. Rights Reserved.
メール占い専門館 (c)NABOO Inc. Rights Reserved.